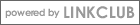Complete text -- "季刊『ココア共和国』vol.14"
02 February
季刊『ココア共和国』vol.14
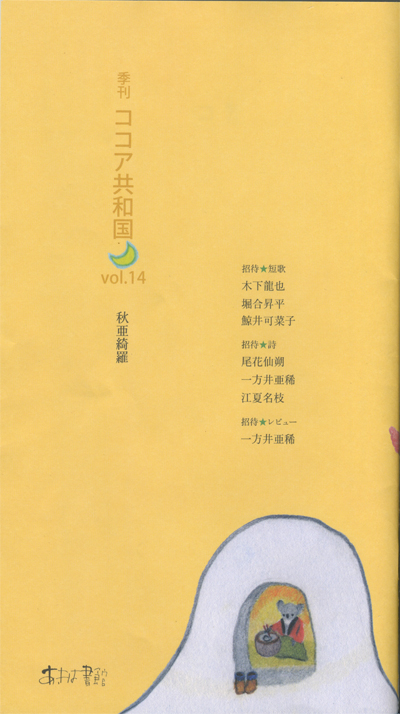
季刊『ココア共和国』Vol.14が届きました。今号は対照的な長編の詩2編が掲載されています。一つは,尾花仙朔氏の「百鬼夜行の世界の闇に冥府の雨が降っている」,もう一つは発行人の秋亜綺羅氏の「ひよこの空想力飛行ゲーム」です。どちらも重い主題を背負っている詩です。そして,すばらしリアリティのある作品だと感動しました。
例えば,尾花氏の作品では,ということで15行目以降を若干引用させていただきます。
ある日抗議の自爆テロ・ロケット弾が旧約の神の国をおびやかす
とすかさず見境のない空爆・ミサイルの報復に
無間地獄が現出する
この世の無間地獄に冥府の雨が降っている
冥府の雨の縫目から きれぎれに
あどけない幼い娘の声がきこえてくる
《オカアサン ワタシノ顔ドコヘ
トンデ行ッタノカシラ?》
《いつも添い寝していた母娘だもの》
―――――と魂の母が応えている
《きっと吹きとばされたわたしの
胸乳のそばでしょうね》
詩「百鬼夜行の世界の闇に冥府の雨が降っている」
第1連15行目〜26行目
この強烈な痛みを喚起する言葉はいったいどこから生まれてくるのだろうか。すさまじい想像力だと思います。痛みを共有するというよりも,痛みを引き受けようとするかのような昇華した強い意志を感じます。尾花氏は,この「冥府の雨が降っている」というフレーズのリフレインを通して,時代の不正義に対し,呪いの言葉を吐いています。まるで,予言者の僕(しもべ)のように,そして全263行余の長大な呪詛の言葉で,世界を覆い尽くそうとしているかのようです。
秋氏はの作品は,冒頭の5行を引用させていただきます。
少女と長いキスをして,やがて舌はくちびるを割って口内をまさぐる。少女のその部屋は
いつも,同じ香りのような,かすかな味がした。唾液で湿った上あごのひだからは,薬の
匂いというか,消毒薬みたいな。化学が生みだしたような甘さと,すこしく苦みを,わた
しの舌の先は感じていた。あ。あれは,少女の体内をなんどもまわっていたセルシンの,
毛細血管からの匂いだったんだね。と,四〇年も過ぎて,キスの味の仕掛けに気がつく。
詩「ひよこの空想力飛行ゲーム」
冒頭5行
人間とは,生きている。死んだ人を,人間とは普通は呼ばない。その意味で,自分が人間なんだと気付く瞬間を詠ったものだと思います。このリアリティは,皮膚を突き破って出たばかりの,生きている真っ赤な血のように,絶対的な斬新さを持っています。そして,私がそう感じてしまったという事実は,最低限,疑いようのないもので,それだけで読者としては,もう十分なのです。こちらも全233行余の長大な詩編です。
この週末,良い詩に出会ったとつくづく思っています。戦慄さえ覚えます。
と,同時に私には,ある疑念が生じました。それは,一体ここまで書く必要があるのだろうかという単純なものです。何も,長く書くのが無駄だということではないのです。それは,どのように表現していいのか,迷いますが,「このようなことを,詩で表現することに何の意味があったのだろうか」ということです。
つまり,尾花氏の作品で、言葉の行の大部分のが費やされる、世界じゅうで起きている不条理,人間性を否定する出来事に対する告発の言葉達。それは,数々のマスメディアが、すでに報道し,数多くの人達が訴えてきたこととなんら変わりはないのではないかということです。
平たく考えれば,すでに言い尽くされたことではないかと思うのです。いや,一人でも多くの人が語る必要があるという意味では,意味はあると思いますが,何故にいまさらながら詩で語るのだろうかということです。普通に話せばいいのではないかと思うのです。その意味を考えれば,詩人として語らなければ,誰も耳を傾けてくれない。逆を書けば,詩人の世界では,まだ意味を持つということに過ぎないのではないか,という疑念です。編集前期で秋氏が書いている「日本の現代詩を代表する・・・・詩人,尾花仙朔」まさに,これに尽きるということなのだと思うのです。
そして,秋氏の詩については,私は以前から「書く意味がない」詩であると思っているのですが,ついに書くことに存在感(意味)を求めてしまった,と感じました。存在そのものが「詩」であったはずの身軽な詩人秋氏が,文字に捕らわれてしまっていると思ったのです。
そういう意味では,冒頭の一連と最後の行の「ひろこ」だけで十分です。頭にひらめいた,そこで終わるべきだったのではないか,ということです。そして,伝えたい人だけに伝える。それだけでもう十分にリアリティがあると思うのです。ただし、それでは秋亜綺羅の「詩」の真骨頂ではなくなります。
どうして詩を書くのだろうか,書きたいから書くのだろう。それも,突き詰めれば,自分のためにのみ書くのでしょう。さらに,どうして発表するのだろうか。それは,一人でも自分の作品を感じてくれる人がこの世に居てくれるだろうという自分が生きる希望があるだろうからだと。じゃあ,どうして普通に言えば良いのに,敢てまわりくどい詩で書こうとするのだろうか。詩で表現しようとするのだろうか。
人間の頭、心の中に隆起するリアリティを、相手の頭、心の中に発生させる。ということ、なのかもしれないと思います。そうだと仮定すると、頭の、心の消耗戦を強いられているこの現実世界に、ぽっと放り出した時に、どれだけ詩がリアリティを持てるのか、はなはだ心もとないと感じた次第でした。
そんな、こんなを深く考えさせられる季刊『ココア共和国』Vol.14 でした。
09:37:32 |
tansin |
|
TrackBacks
Comments
コメントがありません
Add Comments
トラックバック