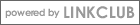Complete text -- "中川有一『累月の空』"
26 August
中川有一『累月の空』

中川有一氏から詩集『累月の空』が届いた。いや、正確に記せば、この詩集の編集者である西田朋さんから届いたと書くべきなのだろう。
私は、中川氏の作品を、彼の詩集『里余の旅』や詩誌『詩想』の中で幾つかを読んでいるが、記憶を辿らなければ、中川氏のこれまでの作品が、どのような姿形だったのか思い出せないでいる。確か、彼の詩「乱月の野辺で」について、かつて自分の詩誌のコラム「情報短信」の中で触れた文章があったはずである。それを探し出して、今、読み返している。そこで感じたことは、今度の詩集は、そのときに私が感じた印象とやや違っているようなのである。詩が塊となり、詩集という山となると、複数の互いの作品が引力のように関係しあって、全体の雰囲気を作り出すようである。私は、一つの樹は語ったが、森を見てこなかったのかもしれない。
言語への強いこだわり、言葉による表現が強い現実感、言い換えれば身体性を持つという詩想ぐるーぷの特徴が、この詩集ではさらりと風景の中に溶けており、「痼り」とはなっていない。つまり、視界を遮る障害物があまり見あたらない。それが“累月の空”という風景なのだと思う。思い込みの強い印象深い言葉遣いというよりも、どちらかというとその「痼り」が溶け出した薄い存在感の中で、言葉の抒情という味わいが風景に滲み出しているという感触を持った。しかし、他の詩人に比べれば、言葉へのこだわりは相変わらず強い。けれど、それは透明な色を持っており、激しく身体を染め上げようとはしない。肉へ食い込むのではなく、当たり前のように周りの景色、あるいはそのときの作者の心の風景に溶け込もうとしているかのようである。それは、まるで死を悟った年老いた象が、自然に帰ろうと草原の中へ消えてゆく「様」のようである。
「累月」とは、これから積み重なる年月ではないであろう。そうではなく、これまでに積み重ねてきた過去の来歴なのだろう。「空」とは、幾重にも塗り込められたその時々の意識の先にある自分を投影した表情なのであるだろう。
記憶とは何だろう
そしてそれにまとわる
実体の不確か
何が真実で
何が不実であるか
境界を確定することなく
その探索は
日々の褶曲に埋もれるだけだ
あるいは そうした理念自体が
幻影にすぎないものなのか
誰が知り得るというのだろう
風霜の履歴から
あえかりに滑り落ちる過去は
等しく密かにこぼれ落ち
やがて荒れ野の地衣を浸し
静かに枯れ土の
表層へと消えて行く
詩「シャルルヴィルへの道」冒頭の一連
この詩集は、自分の来歴を歴史の中に同化させようとする意識と、存在した「個」としての確かなものとしてこの世に残そうとする意識のせめぎ合い、あるいは表裏の繰り返しなのだという気がする。それが「褶曲」という言葉で、何度も現れる。中川氏にとって、出来事とは、全てが揺れ曲がり、過去から今に向かって硬い甲羅と柔らかな白い腹を交互に捻らせながら流れてきている物体である。さらにそれは、未来に向かって、消えてゆくという感覚に収束してゆく。
その意味から、彼の「想い」の最たる表現は、詩「幼年」に結実していると感じる。この詩の心地よさは、いったいどこから来るのだろうか。作者は、自身のことを、他の詩ではドラクロアやランボーなど異形の地への来歴の言葉を借りて間接的に表現しているが、それらの作品はイメージしやすいという意味で、実に心地よい。さらに、その心地よさが、詩「幼年」においては、ギリシャ神話の登場人物の来歴を借りて、自分自身のことに収束していっている。そこには、紛れもない作者自身のものでしかない景色が存在している。
*****************************************************************************
ここまでの文章が、最初に私が詩集『累月の空』を読み始めた感想である。次から記述するのは、その後、何度か静読してから思ったことである。
2003年に出版された中川有一氏の詩集『里余の旅』について、当時、詩集の贈呈を
受けた私は、詩集の中に収められている詩「少女よ 君の中の朝」の冒頭の二行を引き合いに出して、中川氏の詩を「世の中のあらゆるものが意味をなさない、孤独な世界に足を踏み入れた作者というものである。社会に背を向けるということに近いかもしれない。そうすると、周りの様々な出来事が淡々と流れてゆくだけの存在に見えてくる。」と書いた。
今、詩集『累月の空』を読みながら考えてみると、『里余の旅』の中川氏はまだ旅をしている最中だったのだと気づくのである。中川氏は、経歴から推測するに、企業戦士として海外赴任の勤務を長年経験する中で、物理的な糧を得るための与えられた使命を果たしながら、一方では、彼なりの「生きる」という能動的な意味を、自問自答し、無機質に通り過ぎる時間や、周りの景色・事物に違和感を覚えながら、日本語という自己表現の手段を使い、「確かさ」を求め、探していたのだろうと思う。それが、中川氏の“里余の旅”だった。
この感覚は、詩誌『詩想』ぐるーぷの詩人達が持っている時代が作り上げた感性の中にある。例えば故佐藤幸雄氏、例えば故関茂氏、の言葉への強いこだわり、執着に通じる。そういう意味で、詩想ぐるーぷは、ただ単に詩を発表し続けたことをもって記述されるべき存在ではなく、彼らの持つ独特な言葉への接近方法で特色として評価されるべきものであると強く感じる。
詩集『里余の旅』に比して、最新詩集『累月の空』では、中川氏は、旅することをやめている。このような書き方をすると、「後退」しているような印象を与えてしまうが、そうではない。中川氏は、今、一旦ここで立ち止まって、これまで中川氏が見たり、感じたり、思ったことの向こうにある本当の「生きる」(「自分自身」と同義語である。)という意味を、言葉の力というよりも、言葉の抑揚で表現しようと試みている。それは、いみじくも、前詩集『余里の旅』の跋で、故佐藤幸夫氏が「まず、字面をおってできるだけ軽やかに読んで頂けたろうか。」と読者に問わずにはいられなかった、故佐藤氏の最大限の中川氏の詩にたいする敬愛の表現が、今回の詩集で確かなものであったと納得した。
それほどまでに、美しい言葉の響きを、私は心の中に感じながら読むことができた。前詩集の感想で、私が「軽やかにはなかなか読めない言葉達である。まず、リズム感のある流れるような言葉ではない。漢字とひらがなの割合がほぼ5対5で、難解な漢字には字面以上の思念が込められていると思わずにはいられない。言葉に引っかかりが強くあるのだ。その緊張感が、心地よく読めるといえば、そうではあるが。」と書いた印象とは明らかに違っている。この静読の時間は、私にとって至福の時間だったことは紛れもない事実である。ただし、その前に前提となる作業があったことは、書き記したい。それは、中川氏が使う言葉の語感を大事にしようとすると、「読み」や「意味」がわからない言葉がいくつか出てくる。故に、詩集全体を通読する前に、それらの漢字や言葉の読みと意味を調べ上げておく必要がある。
そして、今回の詩集『累月の空』において、私が調べ上げた言葉,つまりは前詩集『里余の旅』で感じた肉感の持った言葉とは具体的に、「累月」「密雲」「虚数」「緑柱石」「玲瓏」「あおとない」「味蕾」「あえか」「凛烈」「褶曲」「傲岸」「「蒼穹」という言葉達だった。これは、同時に私が読めなかった、あるいは知らなかった漢字であり、言葉である。それは、ただの偶然であろうか。小熊だけのことなのであろうか・・・。
最初、これは自分自身の問題、つまり、たまたま偶然なこととであると考えた。そして、そのことは卑近な問題であると思い、考慮せずに詩集全体の読後の感想を書こうとした(それが、前述の最初の感想です)。しかし、どうも思うようには書き切れないでいた。結局、透明感のある美しい詩集だという感想に落ち着き、あまりにもきれいごとで終わってしまいそうなのである。中川氏は、時間を「褶曲」と表現し、何十にも折り重なって湾曲した地層のように捉えている。そして雲はただ白い、あるいは灰色の雲ではなく「密雲」と表現し、幾重にも重なり合った表情を持つ事象と捉えている。一瞬の時も、重なり合った「累月」である。つまり、ただの事物でも、中川氏にとっては、幾重にも「歴史」や「思い」が重なりあった末の表情、に見えているのだろうと気づくのである。
この詩集『累月の空』は、作者を強く感じさせる表情を持っている。選ばれた言葉達は、作者でなければ選べ得なかった言葉達である。例えば、色の三原色があり、どの色も欲しいと思って、全ての色を混ぜ合わせると固有色とはかけはなれた、ただの黒い色となる。それはそれで、見事で味わい深い「黒い色」として表現できる人がいるかも知れないが、その背後に、幾千、幾万という色があったと思わせることが果たしてできるだろうか。それは、前提の言葉を「説明」という形で繰り広げなければ無理であると思う。足りない色があるからこそ、その人にしか出せない色を表現することができるのである。色を重ねるとは、どのような色を使うか、という思考・感覚を働かすと同時に、自分の可能性を切り捨てる行為、つまり限界を知る行為に等しい。だからこそ、その人が浮き出てくる。欠損とは、誰にでも等しい物語なのである。そして、この詩集『累月の空』においては、中川氏の色は、様々な土地で浴びた光を通過して得た色なのであろうと思う。それは、中川氏自身の色であり、中川氏の欠損という己自身なのである。
時代や、自分の生き方に違和を感じ、時計の針を止め、あたかも逆行したかのような言葉を紡ぎ出していた作者が、ここに来て自分自身を素直に肯定し、風景、歴史、過去、時間などの出来事に溶け込もうとしている。そのように生きてゆこうとする姿勢が、この詩集なのだと思う。
故に、私は、この詩集は、次の詩集への決意という意味での序章なのだと思うのである。つまりは、「生きる」ことへの執着である。それは、全くもって、詩集『里余の旅』と『累月の空』の最も激しい類似点でもある。そこには、紛れもない中川有一という人間が潜んでいる。さらに,誤解と言われることを恐れずに書けば、それが言葉に存在感を求めるという彼ら詩想ぐるーぷの詩人達の真骨頂であると、私は思わずにはいられない。
17:21:58 |
tansin |
|
TrackBacks
Comments
コメントがありません
Add Comments
トラックバック